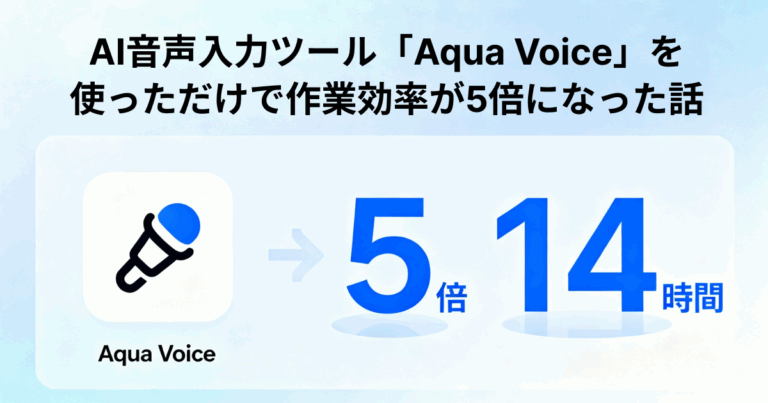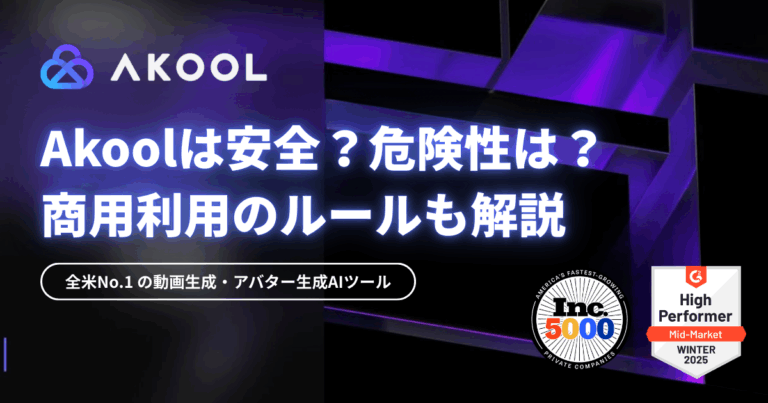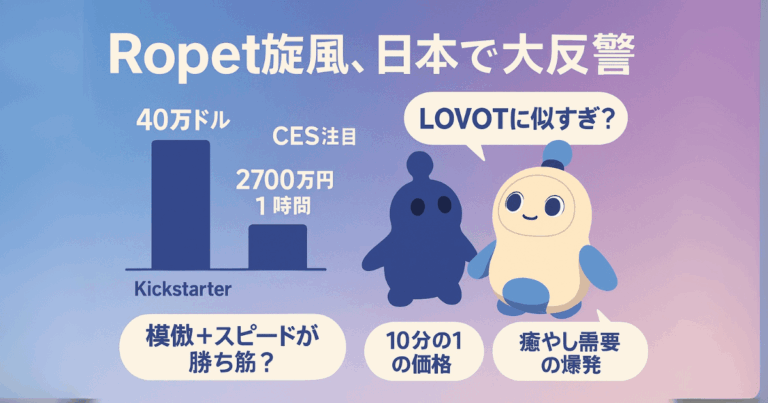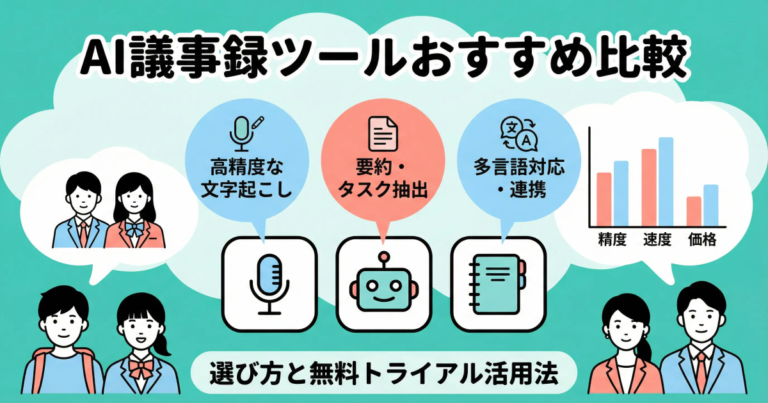生成AIの活用がビジネス現場で広がっています。その中でも、mRNAワクチン開発で注目を集めるモデルナ社はOpenAIと提携し、750以上のカスタムGPT(Generative Pre-trained Transformers)を活用して業務効率化を実現しています。
本記事では、モデルナ社が具体的にどんな場面でChatGPT(生成AI)を使い、どのような成果を上げているのかを紹介します。自社でのAI活用を考えている方の参考になれば幸いです。
モデルナ社が生成AIを導入した背景

新薬開発には、多くのデータ分析、意思決定、コミュニケーションが必要です。モデルナ社はこうしたプロセスをスピードアップし、より少ない人数で大きな成果を生むことを目指し、生成AIツールの導入に踏み切りました。
| 導入のねらい | 内容 |
|---|---|
| 業務効率化 | 情報検索や資料作成の手間を軽減 |
| データドリブン | 臨床試験データ解析を高速化 |
| コミュニケーション強化 | 社内質問への即時回答でストレス軽減 |
モデルナ社におけるChatGPT活用事例
モデルナ社は2023年初頭からOpenAI社と業務提携を開始し、AI技術を活用して業務効率化やイノベーションを推進しています。
この提携により、モデルナ社はOpenAIの生成AIツール「ChatGPT Enterprise」を導入し、研究開発から法務、製造、マーケティング、営業に至るまで、幅広い業務プロセスにAIを適用しています。
具体的なChatGPT活用事例
- mChatの導入
モデルナ社はOpenAIのAPIを活用して独自の社内向けChatGPT「mChat」を開発しました。このツールは従業員の80%以上が利用しており、日常的な業務の効率化に寄与しています。mChatは、社内の情報アクセスを迅速化し、従業員の生産性向上を支援しています。 - Dose ID GPT
臨床試験チーム向けに開発された「Dose ID GPT」は、ChatGPT Enterpriseの高度なデータ分析機能を活用し、最適なワクチン用量を評価するツールです。このツールは、標準的な用量選択基準を適用しながら、根拠や情報源、視覚化されたグラフを生成することで、安全性を最優先しつつ、ワクチン用量プロファイルの最適化を可能にしています。 - Contract Companion GPT
法務チーム向けに開発された「Contract Companion GPT」は、契約書の要約を自動化するツールです。契約文書の重要な条項やポイントを迅速に特定し、法務専門家がより戦略的な業務に集中できるよう支援しています。 - Policy Bot GPT
「Policy Bot GPT」は、社内ポリシーに関する質問に迅速に回答するツールです。従業員が膨大な文書を検索する手間を省き、必要な情報に即座にアクセスできるようにすることで、ポリシーの遵守を容易にし、効率的な意思決定を支援しています。 - プロンプトコンテストとAIフォーラム
モデルナ社では、社員がGPTをカスタマイズし、実践的な問題解決に活用する方法を学ぶ「プロンプトコンテスト」を開催しています。また、週に一度のAIフォーラムでは、2000人の社員が参加し、最新のAI技術や活用事例を共有しています。これらの取り組みは、社員のAIスキル向上と社内コミュニティの形成に寄与しています. - 生成AIチャンピオンズの選出
プロンプトコンテストを通じて選出されたトップのAIパワーユーザー100人を「生成AIチャンピオンズ」として指名し、他の社員へのメンタリングやAIのベストプラクティスの普及を担っています。
社内の情報収集を簡単にする「mChat」
モデルナ社はOpenAIのAPIを活用して、独自の社内向け生成AIツール「mChat」を構築しています。従業員は自然な言葉で質問を投げかけるだけで、必要な情報やナレッジにすぐアクセスできます。
mChatの特徴
- 社内文書や過去データへの素早いアクセス
- 従業員の約80%が利用するシンプルなUI
- 部門横断的なナレッジシェアによる業務効率向上
以前は「どこに何があるのかわからない」という状態で、社内ポータルやファイル共有サーバーを行ったり来たりすることも多かったようですが、mChatの導入後は情報取得の時間が短縮されているといいます。
臨床試験サポート「Dose ID GPT」
新薬開発では臨床試験が欠かせません。モデルナ社は「Dose ID GPT」を開発し、最適なワクチン用量を素早く判断できるようになりました。
Dose ID GPTが実現したこと
- 標準的な用量選択基準に沿った提案
- 根拠となるデータや情報源を同時提示
- グラフや図を用いた視覚的なアウトプット
これにより、研究者はより早く有効な判断を下し、試験結果の確認や再検証もスムーズになりました。
法務業務を支える「Contract Companion GPT」
契約書は法務部門にとって大きな時間コストをかける作業です。「Contract Companion GPT」を使えば、契約書の重要ポイントが自動で要約されます。
このツールを使うメリット
- 契約条項の要点を短時間で把握
- 法務担当者は戦略的な交渉や判断に注力可能
- 書類チェックに割く時間を大幅削減
従来は膨大な契約書を人力で読み解く必要がありましたが、このツールの導入で、法務チームのリソースをより価値の高い業務へ振り向けられるようになっています。
「Policy Bot GPT」で社内ポリシー検索を短縮
社内ルールやガイドラインへのアクセス性向上も重要なテーマです。Policy Bot GPTを使えば、必要な規定を即座に参照できます。
期待できる効果
- ポリシー違反防止
- 意思決定の迅速化
- 膨大なドキュメント検索の手間軽減
情報探しに時間を費やす代わりに、本来注力すべき業務や判断へエネルギーを向けられます。
社員が生成AIを使いこなす仕組みづくり
モデルナ社はツールの整備だけでなく、人材育成にも力を入れています。
- プロンプトコンテスト:社員が自らGPTをカスタマイズし、業務改善アイデアを発表
- AIフォーラム:週1回、約2000人が参加して知見共有
- 「生成AIチャンピオンズ」:優秀なAI活用者100名がメンターとなり、社内全体のスキルアップを促進
こうした取り組みにより、単なるツール導入にとどまらず、組織としてAIを使いこなす文化が根付きつつあります。
生成AIによる成果と今後の展望
モデルナ社の取り組みは、新薬開発のスピードアップや、少ない人員で高い成果を目指す経営戦略にもマッチしています。OpenAIとのパートナーシップを深めることで、新たなツールや機能を柔軟に取り入れ、さらなる効率化・品質向上を狙っています。
まとめ:モデルナ社から学べること
モデルナ社の事例は、生成AIを使って社内ナレッジ共有、研究開発、法務、コンプライアンスなど幅広い業務を改善する好例といえます。ポイントは以下の通りです。
- 業務プロセスごとの最適な生成AIツール選定
- 人材育成やフォーラム開催による継続的なスキルアップ
- 外部パートナーとの連携で機能拡張と柔軟性確保
自社での生成AI導入を検討する際は、こうした事例を参考に、必要な領域から段階的に取り入れ、組織全体に活用文化を広げていくことが有効です。